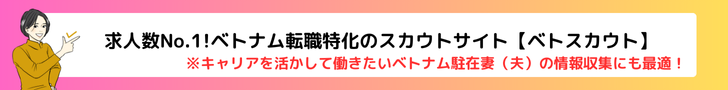駐在妻としてベトナムに行く際に、
現地で何をしよう?
できることなら仕事がしたい!
このように考える妻は年々増加しています。
その背景には、現代の共働きが主流となっている環境や、女性が長期的なキャリア継続を考えているといったことがあります。
今回は、駐在員の妻として、ベトナムに帯同しても働くことができるのか、そのためにはどうすれば良いのか、ポイントと注意点をベトナムで働きたい駐在妻の方に向けて発信したいと思います。
駐在妻でも働くことはできるの?

結論から言いますと、駐在妻はベトナムでも働くことが可能です。
しかし、働くためには夫の会社の規定や納税、就労ビザの問題をクリアする必要があります。
私自身の体験では、実際に駐在妻で働いている人は多くないように感じます。
多くの駐在妻が働きたくても、そうできない、不安で実行できないという現状があるのです。
わからないこと、自分の判断が合っているかどうか不安だと、働くことを躊躇ってしまいますよね。
そんな不安や問題点を洗い出して解説していきますので、駐在妻としてベトナムで働くためにはどうすれば良いのか、ぜひ参考にしてください。
駐在妻ができる仕事
ベトナム駐在妻ができる仕事には大きく分けて2種類があります。
それは、現地の企業に勤める「現地採用」という方法と、日本の企業に勤める(もしくは業務委託で就労する)という方法です。
それぞれの特徴を解説します。
現地採用

現地採用というのは、ベトナム現地法人に雇用されて仕事をする方法です。
現地法人は、日系企業や現地企業など様々ですが、日系企業だと、日本語や今までのキャリアを活用して働けるチャンスが多いでしょう。
現地の社員と共に働くことで、視野が広がり、大きな経験ができる可能性はあるものの、働き方としてはハードなことが多く、子育てや家事との両立が難しい場合があります。
就労ビザや労働許可証はもちろん必要ですが、現地法人が手続きをしてくれる場合がほとんどでしょう。
日本企業の業務委託(フリーランス)

日本企業の業務委託を受けて、フリーランスとして働くという方法もあります。
近年、様々な理由で海外からリモートワークを行う方は多くいますので、そのような仕事の案件も多く存在します。
例えば、SNSマーケティングやライティング、グラフィックデザインやwebデザインの仕事は海外からのリモートワークでも必要とされています。
このパターンであれば、勤務時間の調整がききやすく、育児や家事との両立も可能でしょう。
また、日本企業からの業務委託であれば、仕事も収入も日本国内で発生すると考えますので、基本的にはベトナムでの就労ビザや労働許可証は不要になり、納税も日本国内で行えば、問題ありません。
ビザや納税の問題
次は、気になるベトナムでのビザ、納税について詳しく解説します。
就労ビザについて

ベトナムでの就労ビザ(LDビザ)は、外国人がベトナムで合法的に働くために必要なビザです。
ベトナム国内で正社員として雇用される場合はもちろん、日本国内企業からの出向、駐在として働く場合にも必要です。
また、国内の利益を生み出すような仕事をフリーランス、自営業で行う場合、NPO団体で有給活動を行う場合にも就労ビザが必要です。
ベトナムで就労するためには、まずは労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要になります。労働許可証を取得した後に、就労ビザ(LDビザ)や一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード:TRC)の申請が可能となります。
労働許可証の取得には、以下のどれかの条件を満たす必要があります。
・管理者:現地法人の代表者であり、日本本社で1年以上の勤務経験が必要
・経営者:現地法人の駐在員事務所や支店などの管理者が対象
・専門家:関連分野の大学卒業証明書(または同等の学位)と、その分野での3年以上の実務経験が必要
・技術者:技術または関連分野で最低1年以上の専門教育を受け、3年以上の実務経験が必要
原則として「ベトナム国内で現地法人の指示を受けて働く」場合に就労ビザが必要とされています。
そのため、前述したように、ベトナム現地法人に雇用されず、日本企業との業務委託契約を結んでおり、日本からの指示に基づきリモートワークを行っているフリーランスの場合は、一般的には「就労」とはみなされないため、就労ビザは不要とされています。
納税について
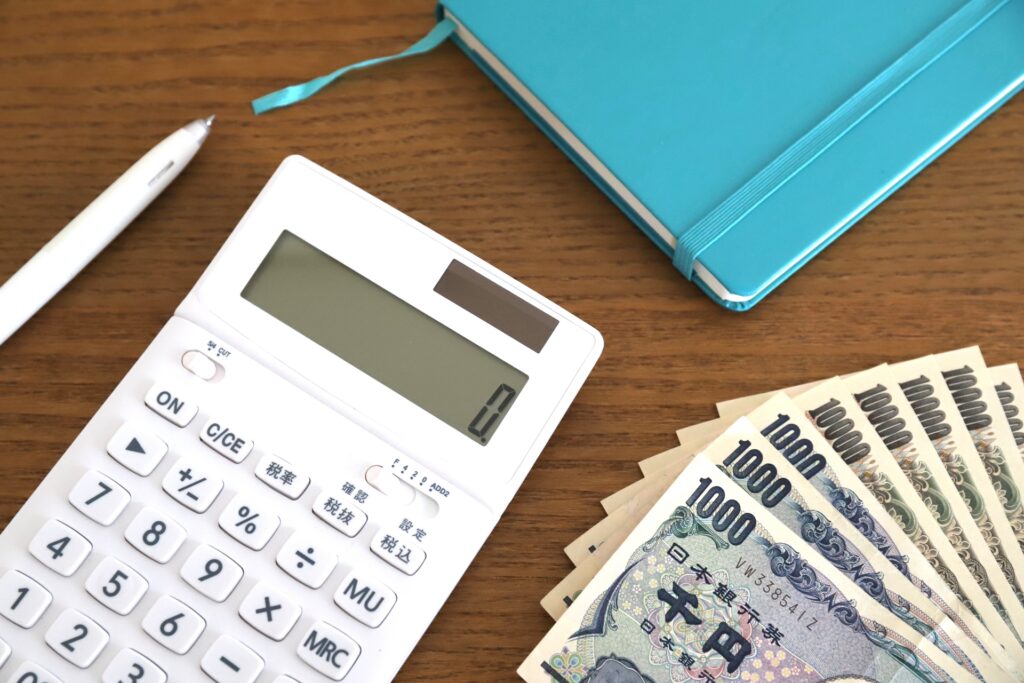
現地採用の場合
ベトナムでは、183日以上の滞在で「税務上の居住者」とみなされ、課税対象が拡大します。
その場合、ベトナム国内外を問わずすべての所得が課税対象になり、日本の銀行口座で給与を受け取っていても、ベトナム側での申告が必要です。
また、納税額は累進課税制で、課税所得が増えるほど税率が高くなります(5%〜35%)。
183日未満の滞在で税務上の非居住者の場合は、ベトナム国内での所得に対して、一律20%の税率が適用されます。
日本企業の業務委託、フリーランスの場合
滞在期間が183日未満の場合、日本からの報酬はベトナムの課税対象外となるのが一般的です。
ただし、ベトナム国内での銀行口座に送金する場合、送金額の記録や税務申告を求められる可能性があります。
滞在期間が183日以上の場合、ベトナムの税法上、「税務上の居住者」として扱われ、日本からの報酬も課税対象となる可能性が高くなります。
ベトナムでは全世界所得課税が適用されるため、日本の企業からの報酬でも課税対象となる場合があります。
ただし、日本とベトナムの間には租税条約が締結されており、「二重課税防止措置」が存在し、日本で納税済みの所得については、ベトナムでの税額控除や免除措置を受けられます。
日本の所得税のルールでは、日本国内もしくはベトナム国内での納税、どちらか一方のみで問題ありません。
ほとんどないケースですが、万が一ベトナム側から納税を求められた場合でも、日本での納税証明を申告することで免除される可能性が高いでしょう。
| ケース | 滞在期間 | 納税の対応 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 日本の企業と契約し、日本で納税 | 183日未満 | 日本での納税のみ | 滞在日数の管理が重要 |
| 日本の企業と契約し、日本で納税 | 183日以上 | 日本で納税+ベトナムでの税務申告(租税条約の控除可) | 二重課税防止の手続きが必要 |
| 日本企業→ベトナム口座へ直接送金 | 183日未満でも課税のリスクあり | ベトナム側で課税対象となる可能性 | 送金目的を明記するのが安全 |
駐在妻はどれくらい稼ぐことができるの?

駐在妻としてどれくらいの収入が見込めるのか、というポイントも働くにあたって非常に重要なポイントです。
もちろん、働ける日数や時間によって、その金額は異なりますが、一般的な目安としてお伝えします。
現地採用の場合
この場合、正社員での雇用がほとんどかと思います。
フルタイム正社員での勤務ができる場合、最低ラインでも20万円程度は稼げるはずです。
役職や職務により、さらに給与がアップする可能性はあり、実はベトナムでの現地採用は日本国内で稼ぐよりも多く稼げる可能性も秘めています。
日本企業の業務委託、フリーランスの場合
業務委託やフリーランスの場合、そのほとんどが時給もしくは案件ごとでの報酬支払いとなるはずです。
週5日、毎日3~5時間程度勤務すれば、およそ10万円以上は稼げるでしょう。
この場合でも、職務や仕事内容によって大きく異なります。
自身のキャリア、稼ぎたい金額をしっかりと踏まえた上で仕事を選ぶようにすることがポイントです。
駐在妻が働くときの注意点まとめ

パートナーは駐在員であることを忘れずに
駐在妻も日本にいた頃と同じように働きたい気持ちは大いにわかりますが、パートナーである夫は「駐在員」として日本の企業から使命を持って派遣されていることを必ず忘れないようにしましょう。
駐在員は一般的に、高待遇・高手当で派遣されていることが多く、それだけ会社に守ってもらえているということになります。
そのため、働こうとする駐在妻とはどうしても境遇に大きな差ができてしまいます。
また、会社は帯同する妻に対しても手当を支払っていることがあります。
例えば、帯同手当、住宅補助など、妻が働けなくなるからという理由で付与されている福利厚生や手当があることを必ず確認しましょう。
はっきりと会社の規定でパートナーの現地就労が禁止されている場合もありますが、妻が働く場合には必ず夫の会社への申告が必要です。
他の駐在妻たちとの関係を大切に
働く駐在妻は、実際にはそう多くはありません。そのため、少数派になってしまいがちです。
ベトナムは日本人駐在員が多くいますので、日本人同士のつながりは切っても切り離せません。
駐在妻同士の関係は、子供がいる場合には学校関係はもちろんのこと、子供たちの交流にも大きく関係します。
子供がいない場合でも、日本人同士で助け合う場面は必ず発生するでしょう。
外国で家族で暮らす以上、いざという時に頼れる知人がいるというのは非常に大きな力となります。
そのため、私は日本人同士の関係を大切にすることが重要だと考えています。
働く駐在妻は羨ましがられたり、他の人と違うという理由でコミュニティから外れてしまいがちですが、自分から離れていくのではなく、働きながらもしっかりと関係性を保つようにしましょう。
納税関係は必ずクリアに
前述しましたが、納税関係をクリアにすることは、海外で働くためには非常に重要です。
無事採用され、仕事が見つかり、夫の会社にも許可をもらえたところで終わりではなく、納税をどのように行えばいいか、必ず働く前にクリアにしておきましょう。
日本国内で納税を行う場合には、何かあった時のために必ず納税証明書を保管しておきましょう。
今回の記事の内容が、海外でも働きたい駐在妻の方々の参考になっていますと、嬉しく思います。