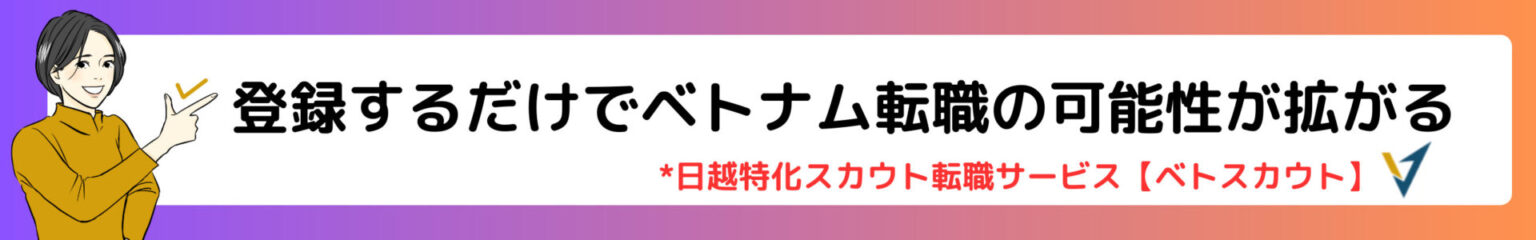ベトナムの食文化の中でも特に議論を呼ぶ話題である「犬肉(ティット・チョー/Thịt chó)」について、現地在住4年目のライターとして客観的な視点から解説します。
この記事では、ベトナムにおける犬肉消費の歴史的背景、現在の状況、そして近年の変化について詳しく紹介します。
観光や駐在でベトナムを訪れる方々に、ベトナム文化を深めていただくための情報をお届けします。
ベトナムにおける犬肉文化の歴史と背景
ベトナムでの犬肉消費には長い歴史があります。主に北部地域を中心に根付いてきたこの習慣は、単なる食文化以上の意味を持っています。

歴史的背景
ベトナム北部では、数百年前から犬肉が食されてきました。中国からの文化的影響と、かつての食糧難の時代に栄養源として重宝されたことが始まりとされています。特にハノイ周辺の農村地域では、伝統的な習慣として定着してきました。
興味深いのは、犬肉の消費には季節性があることです。伝統的には月の満ち欠け(陰暦)に合わせて食べる習慣があり、特に月末に食べると「不運を払う」とされてきました。また、冬季に強壮効果を期待して消費量が増える傾向があります。
文化的位置づけ
ベトナム社会において、犬肉は一般的な肉とは異なる特別な位置づけがあります。北部では「ティット・チョー」(Thịt chó)と呼ばれ、特に男性の間で強壮作用があるとされ、友人同士の集まりや特別な機会に食べられることが多いです。
一方で、ベトナム南部(特にホーチミン市周辺)では、伝統的に犬肉を食べる習慣は北部ほど一般的ではありません。地域差が大きく、北部出身者が経営する専門店が点在している程度です。
宗教的・文化的観点
ベトナムの伝統的な信仰においては、犬は忠誠や守護の象徴とされる一方で、特定の月日に食べることで厄除けになるという二面性があります。仏教の影響が強い地域では、犬肉の消費に抵抗を示す人々も少なくありません。
近年では、特に若い世代や都市部の住民を中心に、ペットとしての犬への認識が高まり、犬肉消費に対する見方も大きく変化しています。ハノイ市内でも、若者の間では犬肉を食べない選択をする人が増えています。
参考データ:ベトナム農業農村開発省の伝統食文化調査
http://www.mard.gov.vn/en/Pages/default.aspx
現代ベトナムにおける犬肉の消費実態
現代ベトナム社会における犬肉消費の実態は、都市部と農村部で大きく異なります。また、世代間でも考え方の違いが顕著になっています。
消費地域と規模
犬肉の消費は主に北部(ハノイ、タイビン省、ナムディン省など)に集中しています。ハノイ市内だけでも推定1,000店以上の犬肉専門店があるとされていますが、公式な統計はありません。
一方、中部や南部では比較的少なく、ホーチミン市内では主に北部出身者向けの店が点在する程度です。農村部では自家消費や地域内での小規模な取引が中心となっています。
年間の消費量については正確な統計はありませんが、動物保護団体の調査によると、ベトナム全土で年間約500万頭の犬が食用として消費されているという推計もあります。
ただし、この数字には議論の余地が残ります。
価格と流通
犬肉は一般的な肉類と比較して高価です。2023年現在、市場価格で犬肉は約60,000〜100,000ドン(約360〜600円)/100gで取引されており、これは牛肉とほぼ同等か、場合によってはそれ以上の価格です。
流通経路については不透明な部分が多く、国内での繁殖に加え、隣国からの密輸も指摘されています。これが食の安全性や動物福祉の観点から問題視される一因となっています。
提供形態と料理
犬肉専門店(Quán thịt chó)では、以下のような調理法で提供されることが一般的です。
チョー・ハップ(Chó hấp):蒸した犬肉
チョー・スオン・サウ(Chó xào sả ớt):レモングラスと唐辛子で炒めた犬肉
ラウ・チョー(Lẩu chó):犬肉の鍋料理
これらは通常、ライスワイン(Rượu)と共に提供され、男性グループでの会食で楽しまれることが多いです。店の外観は「チョー」(Chó)と書かれた看板で識別でき、観光地から少し離れた地域に多く存在します。
現地の人々の意識
私が実施した非公式な聞き取り調査では、若い世代(特に30歳以下)と都市部の住民は犬肉を食べない傾向が強まっています。教育水準の高い層や国際的な接点を持つ人々の間では、この習慣に対して批判的な見方も広がっています。
一方で、中高年層や伝統を重んじる層では、文化的習慣として受け入れられている面もあります。「自分たちの文化を外部から批判されたくない」という意識も根強く存在します。
法規制と動物福祉の観点
ベトナムにおける犬肉消費に関する法規制は、近年大きく変化しつつあります。国際的な圧力や国内の意識変化を背景に、様々な取り組みが進んでいます。

現行の法規制状況
2018年まで、ベトナムには犬肉の消費や取引を直接規制する法律はありませんでした。しかし、2018年にハノイ市当局が2021年までに市内での犬肉販売を段階的に禁止する方針を発表し、注目を集めました。
この方針は完全には実施されていないものの、都市中心部での新規店舗開設に対する制限や、衛生基準の厳格化などの形で徐々に進められています。
食品安全の観点からは、2020年に農業農村開発省が犬肉取引に関する衛生基準を強化する通達を出しており、無許可の屠殺や不衛生な取り扱いに対する取り締まりが強化されています。
動物福祉の課題
犬肉産業に関連する動物福祉の問題点として、以下が指摘されています。
・輸送時の過密状態や不適切な扱い
・屠殺方法の残酷さ
・ペット犬の盗難と食用への転用
・狂犬病などの疾病管理の不十分さ
特に狂犬病の問題は公衆衛生上の懸念材料となっており、WHOやFAOなどの国際機関も注意を喚起しています。ベトナム保健省の統計によると、年間約70人が狂犬病で命を落としており、その一因として不適切な犬の取り扱いが挙げられています。
国際的な圧力と国内の変化
アジア動物友の会(Animals Asia)やヒューメイン・ソサエティ・インターナショナル(HSI)などの国際的な動物保護団体は、ベトナム政府に対して犬肉取引の規制強化を求める活動を展開しています。
2018年には、米国議会でベトナムを含むアジア諸国での犬・猫肉取引を非難する決議が採択され、外交的圧力も高まっています。
一方、ベトナム国内でもペット文化の浸透に伴い、動物保護団体が増加しています。「Vietnam Animal Aid and Rescue」や「Vietnam Cat Welfare」などの団体が、啓発活動や保護活動を展開しています。
参考データ:ベトナム保健省の狂犬病統計
https://moh.gov.vn/
観光と文化理解のバランス
ベトナムを訪れる外国人観光客や駐在員にとって、犬肉文化は時に衝撃的な体験となることがあります。しかし、文化的感受性を持ちながらこの問題を理解することが重要です。

観光客への影響
犬肉店の存在は、一部の観光客にとって不快感を与える要因となっています。特に欧米やペット文化が根付いた国からの観光客には、文化的ショックとなることも少なくありません。
ベトナム観光局の内部調査によると、一部の観光客が犬肉の販売を目にしたことで、旅行体験の評価が下がったケースも報告されています。これを受けて、主要観光地周辺では犬肉店の出店を制限する動きも見られます。
ハノイやホーチミンなどの主要都市では、観光客が多く訪れるエリアから犬肉専門店が徐々に減少しており、より住宅地域や郊外に移動する傾向があります。
文化的理解と尊重
文化的背景を理解することと、それを支持することは別問題です。訪問者として重要なのは、自分の価値観を押し付けることなく、異なる文化的背景を理解しようとする姿勢です。
ベトナム人の中にも様々な意見があることを認識し、一括りに「ベトナム文化」として単純化しないことが大切です。
若い世代を中心に変化が起きていることも忘れてはなりません。
訪問者が気をつけるべきポイント
ベトナムを訪れる外国人は、以下のようなポイントを知っておくと役立つでしょう。
・地元の人との会話で犬肉の話題が出た場合は、批判的な態度を取らず、理解を示しながら自分の立場を説明するのが良いでしょう
・ペットとして犬を連れている場合は、特に北部の農村地域では常に目を離さないようにすることが賢明です
・動物保護活動に関心がある場合は、現地の保護団体でボランティアする機会もあります
私自身、現地在住者として感じるのは、この問題に対する意識は徐々に変化しているということです。特に若い世代や都市部では、犬をペットとして大切にする文化が広がっています。
変化する食文化と将来展望
ベトナムの犬肉文化は過渡期にあり、社会的・経済的変化とともに大きく変わりつつあります。今後の展望について考えてみます。

若い世代の意識変化
都市部の若い世代を中心に、犬肉を食べない選択をする人が増えています。ホーチミン市の大学生100人を対象にした非公式調査では、約70%が「犬肉を食べたことがない」と回答し、約80%が「将来的に食べるつもりはない」と答えています。
この変化の背景には、以下の要因があります。
・ペット文化の普及(特に都市部の若い家族の間でペット飼育が増加)
・SNSを通じた動物福祉意識の高まり
・国際的な交流の増加による価値観の変化
・教育水準の向上
経済発展と食文化の変化
ベトナムの急速な経済発展は、食文化にも変化をもたらしています。かつては「特別な機会に食べる高価な肉」だった犬肉は、より多様な食の選択肢が増える中で、その特別な地位を失いつつあります。
また、中間層の拡大とともに、ペットとしての犬に費やす金額も増加しています。ハノイやホーチミンでは高級ペットショップやペット向けサービス業が急成長しており、犬の社会的位置づけが変化していることを示しています。
政府の方針と国際関係
ベトナム政府は国際社会との関係強化を重視しており、国際的なイメージ向上のために犬肉取引の規制を徐々に強化する方向に動いています。特に観光業の発展を重視する政策との整合性から、主要都市や観光地では規制が進む可能性が高いでしょう。
2020年に新型コロナウイルスのパンデミックを受けて、野生動物の取引規制が強化されましたが、これが将来的に犬肉取引の規制にも波及する可能性があります。
将来犬肉文化はどうなるのか
現在の傾向が続けば、今後10〜20年でベトナムにおける犬肉消費は大幅に減少すると予測されています。具体的には以下のような変化が起こりうるでしょう。
・都市部での犬肉店の更なる減少
・若い世代を中心とした消費の減少
・法規制の段階的強化
・ペット文化のさらなる普及
ただし、農村部や伝統を重んじる地域では、変化はより緩やかになる可能性があります。文化的変化は一朝一夕には起こらず、世代交代とともに徐々に進んでいくでしょう。
まとめ
私自身、4年間のベトナム滞在で感じるのは、この問題に対する社会の姿勢は近年確実に変化しているということと、ベトナム人の中にもさまざまな考えの人がいるということです。
日本人だからと言って、毎日寿司は食べませんし、着物は着ていませんよね。
そのような感覚と同じだと思います。
犬をペットとして大切にする文化が急速に広がる一方で、伝統的な習慣も依然として存在するという、過渡期特有の二面性が見られている状況だと感じています。
ベトナムの犬肉文化は、単純に「良い・悪い」で判断できるものではなく、歴史的・文化的背景を踏まえた複雑な問題です。訪問者としては、文化的感受性を持ちながらも、動物福祉の観点からの懸念も理解することが大切です。
そして何より、ベトナム社会自体が変化の過程にあることを認識し、一面的な見方を避けることが大切だと思います。
参考データ:ベトナム観光総局の観光産業報告
http://vietnamtourism.gov.vn/