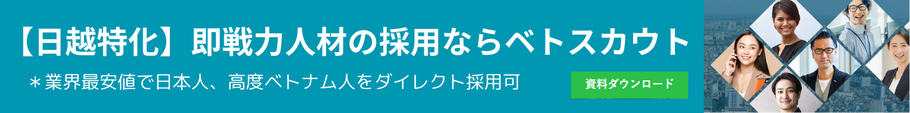ベトナムの教育は、日本とは異なる独自の特徴を持っています。
義務教育から大学までどんなことを教えられ大切にしてきたかが、その後の就業態度や労働倫理につながっています。
この記事では、ベトナム人が社会人になるまでにどんな教育を受けたきたのか、日本の教育制度との違い、教育がベトナム人の就業態度や労働倫理にどんな影響を与えているかを解説します。
上司部下としてベトナム人と上手に接したり、企業としてベトナム人の特性を理解し、適切な環境を整えたり適切な対応を行ったりするためにも、参考にしてください。
※本記事は、ベトナム市場に精通した現地在住8年の日本人の知識と、ベトナム・ハノイ国家大学を卒業したベトナム人(Thanh Hangさん)の意見を踏まえ、2024年9月に更新しました。
ベトナムの教育制度
学校体系と学年暦
ベトナムの教育制度は、義務教育から高等教育までの体系が整備されており、社会人になるまでの教育過程は次のように構成されています。
| 就学前教育 | 3歳から6歳までの幼児を対象に、幼稚園や保育園で子どもたちの心と身体を育み、豊かな人間性を育み、学習の基盤を築く教育が行われます。 *保育園(3ヵ月~3歳)、幼稚園(3歳~6歳) |
|
| 義務教育 | 初等教育 | 日本の小学校相当。6歳から11歳までの5年間。 |
| 前期中等教育 | 日本の中学校相当。11歳から15歳までの4年間。 | |
| 後期中等教育 | 15歳から18歳までの3年間で、高校に相当。 | |
| 高等教育 | 大学、短大、専門学校などが含まれ、学士号を取得するためには通常4年間の学習が必要です。 | |
ベトナムで大学を目指す高校生は、高校卒業試験を受け、高校教育を修了した証明書が必要になります。試験は、全国共通の問題で、同一の時間帯に実施されます。
更に、一部の大学では、高校の成績証明書や独自の入学試験で合否を決めることもあります。独自の試験を実施する大学は、ハノイ国家大学、ハノイ工科大学、ホーチミン市国家大学といったベトナムのTOP大学がほとんどです。(2024年度は全国で8大学が独自試験を実施と報告されています。)
ベトナムの大学進学率は、2022年には48.09%、2023年は約53.1%です。
ベトナムの教育の4つの特徴
特徴①全国統一の高校卒業試験がある
日本のように大学進学のための全国統一試験(センター試験)制度は2015年で廃止され、代わりに高校卒業試験が全国統一で実施されるようになりました。この高校卒業試験により、全国的な教育水準の均一化が図られています。
試験結果は、高校を卒業できるかどうかの判定と、大学・短大の学校側が学生を選ぶときの判断材料として活用されます。
高校卒業試験は全国どこでも同じ問題で行われますが、大学・短大側は独自の方法で学生を選びます。高校卒業試験の点数だけでなく、高校時代の成績や、能力を測る別の試験結果、面接なども合わせて、総合的に学生を選抜します。
特徴②職業教育
現在のベトナムでは、高校卒業後の進路として、専門学校や短期大学など、様々な職業訓練学校や中等技術職業学校を選ぶことができます。これらの学校は、卒業後すぐ就職できるように、実践的なスキルを学ぶ機会が提供されています。
ただ大卒の学位がより価値があると見なされる傾向が強く、大学進学を選択する学生も多いのも事実です。
特徴③教育熱心な文化
ベトナムでは教育が非常に重視されており、家庭の教育支出は高い割合を占めています。特に数学や英語の教育に対する関心が強く、国際数学オリンピックなどで毎年メダルを獲得するなど成果も顕著です。
特徴④授業時間数と教科の比重
| ベトナム | 日本 | |
| 小学校の年間合計授業時間数 | 約653時間+補習授業多 | 約760時間 |
| 中学校の年間合計授業時間数 | 約853時間+補習授業多 | 約845時間 |
ベトナムの小学校の合計授業時間数は約653時間と、日本の約760時間より少なく、中学校はベトナム約853時間(日本は約845時間)と大差がない時間数になっています。
ただベトナムでは、正規の授業に加えて、放課後や週末にも補習授業を受ける生徒が非常に多いです。そのため、生徒たちが実際に勉強している時間は、規定の授業時間よりもはるかに長くなっています。
現在、ベトナムでは、数学、国語、英語が主要科目として重視され、多くの授業時間が割かれています。高校に進学すると、生徒たちは自分の能力と興味に基づいて、主に3つのコース「理系コース(数学、物理、化学)」「文系コース(文学、歴史、地理)」「普通コース(全科目を学習)」に分かれます。
理系コース、文系コースでもすべての科目を勉強しますが、コース分けは、生徒の希望と中学校での成績に基づいた優先順位がつけられます。一般的に、理系コースと文系コースで学ぶ生徒たちは優秀だと見なされています。
ベトナムでは体育や芸術などの科目は、依然として軽視される傾向にあります。
ベトナム教育制度の問題点と進化
ベトナム教育制度の問題点
ベトナムの教育制度の問題点として代表的なのは以下3つ。
①過度な試験のプレッシャー:生徒たちは過度に試験の点数ばかりを気にしてしまい、本来身につけるべきスキルを伸ばせていない状況です。
②学習内容が詰め込み型:日本も詰め込み型ですが、日本以上に詰め込み型で、社会に出てから必要とされる自らが考えて行動する能力を習得できていません。
③都市部と地方での教育格差:都市部と地方では教師の質に差があり、地方では施設や設備の不足、そして教師不足も深刻です。特に、幼稚園や小学校の教諭が足りていない状況です。
デジタル教育の導入が進む中で、地方ではオンライン学習が進まないなど解決すべき課題が残っています。
ベトナム教育制度の進化・発展
近年、ベトナム政府は教育制度の改善に取り組んでおり、①教育カリキュラムの刷新、②情報技術の活用、③STEM教育(科学、技術、工学、数学)が推進されています。
①教育カリキュラムの刷新: 教育訓練省は、生徒の能力と資質を全般的に育成することを目的とした、新しい中等教育カリキュラムを実施しています。
②情報技術の活用: オンライン教育や教育管理など、情報技術は教育のあらゆる場面でますます活用されています。
③STEM教育の発展: 将来の労働市場のニーズに応えるために、STEM教育(科学・技術・工学・数学)の発展に重点が置かれています。
ベトナムの教育制度は、経済成長とともに進化し続けており、今後の発展が期待されています。教育を受けた若者たちは、国際的なビジネス環境でも競争力を持つ人材として活躍することが求められています。
ベトナムの教育の特徴と就業へ与える影響

学習意欲と向上心
ベトナムでは、幼い頃から「勉強しなければ、良い仕事に就いて安定した収入を得ることは難しく、貧困から抜け出すこともできない」と、親や周囲の大人から繰り返し教えられます。
このため、ベトナム人は一般的に学習に対して真剣であり、向上心が強い傾向があります。
こうした教育により、ベトナム人は日本人と同様に真摯に学業や仕事に向かう傾向があり、日本企業でも迎え入れられやすい環境が整っています。
職場において自己成長を求める姿勢があり新しい技術の習得にも積極的です。特に技術職においては、単純作業ではなく、新しい挑戦を求める傾向が強く、キャリアアップを目指して転職を考えることも多いです。
所属意識と労働観
教育を通じて、ベトナム人は家族やコミュニティの重要性を強く認識しています。
このため、職場でも同僚や上司との関係を重視し、チームワークを大切にする傾向があります。職場の人間関係を良好に保つことが、仕事へのモチベーションを高める要因となっています。
一方で、ベトナム人は家庭を非常に重視します。
ベトナム人の家族優先意識は高く、病気の家族の世話をするため、あるいは子供の重要なイベントに参加するために、仕事を休むことをいとわなかったりします。
また、残業に対する意識が日本人とは少し異なります。
多くの日本人が「ベトナム人は家庭の時間を優先し、過度な残業を避ける傾向がある」と思い込んでいますが、最近は家族の生活水準向上のために残業して稼ぎたい方も増えています。
ベトナム人にサービス残業(残業代無し)を強いると、日本人以上に嫌がられることは肝に銘じておきましょう。
実践的な知識の適用
ベトナムの教育制度では、理論的な知識が重視される一方で、実践的なスキルの習得が不足していることがあります。これが、職場での知識の適用に課題をもたらすことがあります。特に、教育で学んだ内容を実際の業務に活かすことが難しいと感じることが多いです。
そのため、企業側は教育や研修を通じて、実務に即したスキルを身につける機会を提供することが重要です。定期的な研修や実地訓練を行うことで、ベトナム人労働者が職場でのパフォーマンスを向上させることが期待できます。
ベトナムの教育制度と労働倫理への影響

勤勉さと真面目な労働態度
ベトナムの教育制度は、勤勉さや真面目さを重視する文化を育んでいます。学生は学校での学習を通じて、努力や忍耐の重要性を学びます。このため、労働市場に出た際、ベトナム人は一般的に真面目に仕事に取り組む姿勢を持っています。
教育を受けたベトナム人は、職場での規律や時間厳守を重視し、業務に対する責任感が強い傾向があります。これにより、企業は彼らの労働倫理を高く評価することが多いです。
規律と社内規範の重視
教育を通じて、ベトナム人は規律や社内規範を重視する意識を持つようになります。これは、企業における勤務時間の遵守や社内ルールの徹底に繋がります。
特に、職業訓練校や専門学校での教育は、実践的なスキルとともに、職場での行動規範を学ぶ重要な場となります。これにより、企業は労働者が規則を守り、円滑に業務を遂行することを期待できます。
相手を尊重し、情を重視
ベトナムには「nể nang(ネーナン)」(情を重視し、遠慮や義理を生みやすいという意味)という、相手を尊重し気遣う文化があります。例えば、会社で地位のある人や上司と親しい人が遅刻した場合、周囲は「nể nang」の精神から大目に見がちです。 「あの人は役職もあるし…」と考え、遅刻を許してしまうのは、ベトナムではよくある光景です。
他にも、nể nang(ネーナン)の例として、
・取引先の無理な要求を受け入れてしまう
・同僚の仕事を手伝ってしまう: 同僚から仕事のヘルプを頼まれた時、自分の仕事が忙しくても、断ると人間関係が悪くなることを心配して手伝ってしまう。
・上司の誘いを断れない
などが挙げられます。
安全意識と職場環境
日本と比較して、ベトナムでは安全や衛生に関する意識が低いとされることがあります。特に、整理整頓や身だしなみの面で、日本の【5S(「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」)】などの概念が浸透していないため、企業は安全教育や職場環境の改善に努める必要があります。
上司や年上を敬う
ベトナムでも日本と同様に、職場では上司を敬い、与えられた仕事を積極的にこなすことが一般的です。
上司の指示に従うのは、上司の権威だけでなく、上司のほうが経験や知識が豊富で、その指示に従うことがチーム全体のためになると信じているからですが、盲目的に何でも従うわけではありません。
指示が不明確だったり、理にかなっていなかったり、全体の利益に反する場合は、主体性と責任感を持って自分の意見を言ったり、別の方法を提案することもあります。
教育制度から読み解くベトナム人労働者が得意な点・苦手な点

ベトナム人の得意な点
勤勉さと真面目な労働態度: ベトナムの教育は勤勉さや真面目さを重視する文化を育んでおり、ベトナム人は一般的に真面目に仕事に取り組む姿勢を持っています。
向上心と新しい技術への意欲: ベトナム人は常に自己改善を目指し、職場でも新しい挑戦を求める姿勢が見られます。
チームワークとコミュニケーション: ベトナムの教育は協調性やチームワークを重視する傾向があり、職場でも同僚や上司との良好な関係を築くことが期待されます。
規律と社内規範の重視: ベトナム人は規律や社内規範を重視する意識を持ち、勤務時間の遵守や社内ルールの徹底に繋がります。
日本への好印象と技術習得への意欲: ベトナム人は日本に良い印象を持ち、日本の技術を学びたいという意欲が強いです。
ベトナム人の苦手な点
仕事に対する考え方の違い: 昼休みの長さや残業に対する意識の違いから、日本企業との摩擦が生じる可能性があります。
安全意識の低さ: 近年ではヘルメット着用の義務化や交通安全教育の強化など、ベトナムでも安全意識の向上も見られますが、まだまだ日本より安全や衛生に関する意識が低いのが現実です。
若者を中心に安全意識は高まってきていますが、ベトナム人に工事現場での安全管理、食品衛生面の管理を担当する場合は日本基準をしっかり伝えることを意識しましょう。
実践的なスキルの不足: ベトナムの教育では理論的知識が重視される一方で、実践的なスキルの習得が不足していることがあります。そのため、ベトナム人は、充実した社員教育やスキルアップの機会が得られる職場環境を強く求めています。
まとめ
ベトナムの教育制度は、幼児から大学までの段階が整備されています。義務教育は9年間で、全国統一試験が進学先を決定します。職業教育も充実しており、熱心な教育文化が根付いています。
こうしたベトナムの教育制度は就業態度・労働倫理に多様な影響を与えています。
勤勉さと真面目な労働態度、新しい技術への意欲、チームワーク、規律重視は良い点ですが、仕事に対する考え方の違い、安全意識の低さ、実践的なスキルの不足を埋め合わせる必要があります。
企業はこの特性を理解し、ベトナム人が活躍しやすい職場環境を整えたり適切な対応を行うことが求められるでしょう。
本記事では、多くのベトナム人に共通する傾向とその根拠となる教育制度について解説しました。ベトナム人の全体的な特徴を掴むには参考になるかと思います。
※但しひとえにベトナム人といえども、性別や年齢、出身地(北部or中部or南部)をはじめ、育った家庭環境、経験などで性格や価値観は一人一人違うことは忘れないでください。
この記事がお役に立てば幸いです。